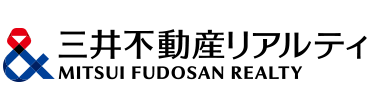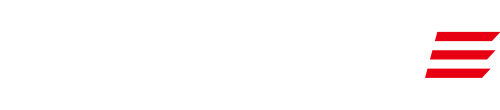電気自動車のメリットは?魅力や特徴、注意点を解説
電気自動車は環境やコスト、性能などさまざまな面においてメリットがあります。この記事では、電気自動車の特徴やメリット・デメリットの解説に加え、気軽に試す方法についても紹介します。
電気自動車とは?
電気自動車とは、文字通り電気の力で走行する自動車のことです。従来のエンジン車はガソリンや軽油などの燃料を燃焼させることで駆動力を得ますが、電気自動車はバッテリーに蓄えられた電気をモーターに供給し、その力でクルマを動かします。
ちなみに、電気自動車(EV)は4種類に分けられます。具体的には、バッテリー式電気自動車(BEV)、ハイブリッド自動車(HEV)、プラグインハイブリッド自動車(PHEV)、燃料電池自動車(FCEV)で、以下の一覧表のとおりです。
|
項目 |
種類 |
略称 |
特徴 |
|
電気自動車(EV) |
バッテリー式電気自動車 |
BEV(Battery Electric Vehicle) |
バッテリーに蓄えた電気を利用し、モーターを駆動して走る |
|
ハイブリッド自動車 |
HEV(Hybrid Electric Vehicle) |
エンジンと電気モーターの2つを効率よく使って走る |
|
|
プラグインハイブリッド自動車 |
PHEV(Plug-in Hybrid Electric Vehicle) |
エンジンと電気モーターの2つを備え、さらに外部電源からの充電もできる |
|
|
燃料電池自動車 |
FCEV(Fuel Cell Electric Vehicle) |
水素と酸素を反応させて電気をつくり、モーターを駆動して走る |
今回は、電気の力のみを使って走行するバッテリー式電気自動車(BEV)について、電気自動車と記述しながら解説します。
電気自動車が注目される理由
近年、電気自動車が注目されている主な理由は、環境問題への対応力です。地球温暖化対策の強化に伴い、世界各国が温室効果ガスの排出削減に向けた取り組みを進めています。その中で、電気自動車は走行時に二酸化炭素(CO2)を排出しないため、環境負荷の低減に貢献すると期待されています。
また、多くの国が対策の一環として、エンジン車から電気自動車への移行(EVシフト)を推進していることも、電気自動車の注目度を高める大きな要因のひとつです。各国の政府が補助金の導入や充電インフラ整備を進めることで、EV市場は今後さらに拡大していくと考えられます。

電気自動車のメリット
電気自動車のメリットには、主に以下の6つが挙げられます。
- 環境にやさしい
- 振動や騒音が少なくスムーズに加速できる
- 燃料費を抑えやすい
- 自治体によっては補助金・減税の対象になる場合がある
- 車種によっては災害時の電源に利用できる
- エンジン車と比べるとメンテナンスがしやすい
それぞれ解説していきます。
環境にやさしい
電気自動車のメリットは、走行中に二酸化炭素(CO2)や窒素酸化物(NOx)などの排気ガスを一切排出しないことです。日本政府は2050年までにカーボンニュートラル(脱炭素社会)の実現を目指しており、電気自動車は「環境にやさしいエコカー」として大きな期待が寄せられています。今後は、電力の供給や製造過程で発生する二酸化炭素(CO2)の排出量が課題となるでしょう。

振動や騒音が少なくスムーズに加速できる
電気自動車は電気モーターによって動くため、快適で静かな車内環境を実現します。エンジン車は、燃料(ガソリンや軽油)と空気を混ぜて燃焼させた熱エネルギーを動力とします。そのため、加速に一定の時間がかかるほか、振動や騒音を避けられません。一方で、電気自動車は充電した電気でモーターを回転させるため、アクセルを踏んだ瞬間からスムーズに加速できるうえ、振動や騒音が気にならない快適な乗り心地です。
燃料費を抑えやすい
電気代はガソリン代に比べて安価であり、充電方法によっては、同じ距離を走行したときのランニングコストが大幅に節約できる場合があります。
さらに、エネルギー効率が格段に高い点も特徴です。エンジン車が燃焼により得た熱エネルギーの20%~25%ほどしか動力に変換できないのに対し、電気自動車は電気エネルギーの80%程度を効率的に利用できるため、燃料費を抑えることが可能です。

自治体によっては補助金・減税の対象になる場合がある
電気自動車は、政府や自治体が提供する電気自動車の購入補助金や、自動車税の減免制度が適用されるケースも多くあります。また、環境性能に優れた車両に対する税制優遇も一般的なので、これらを活用すれば初期費用の負担を軽減できる可能性は高いでしょう。ただし、補助金や減税の内容は自治体によって異なるため、事前に確認することが重要です。
車種によっては災害時の電源に利用できる
電気自動車のメリットとして、災害による停電時に車載バッテリーを非常用電源として活用しやすいことも挙げられます。たとえば、非常時にはケーブルを介してバッテリーから機器に電力を供給する方法があるほか、専用システムを使用すれば、家庭に直接電力を供給することも可能です。ただし、この機能の有無はメーカーや車種によって異なるため、購入前に確認しておくことが大切です。
エンジン車と比べるとメンテナンスがしやすい
電気自動車は、ガソリンや軽油で動くエンジン車と異なり、エンジンオイル交換や点火プラグ交換(ガソリンエンジン)が不要のため、部品点数が少なく整備頻度やコストが低い点もメリットです。また、電気自動車には「回生ブレーキ」が搭載されています。回生ブレーキは、車両の減速時に発生する運動エネルギーを回収して、電力として再利用する仕組みです。エンジン車よりもブレーキパッドの消耗が抑えられるため、交換やメンテナンスにかかる費用を抑えやすいというメリットもあります。

電気自動車のデメリット
電気自動車のデメリットは主に以下の3つが挙げられます。
- 初期費用が高い
- 充電スポットが少ない
- 航続可能距離が短い
それぞれ解説していきます。
初期費用が高い
電気自動車は、エンジン車と比較して初期費用が高いというデメリットがあります。特に車両本体は最新の技術や高性能かつ大容量のバッテリーを搭載しているため高価です。さらに、充電設備の導入や購入となれば、導入時のコストを十分に考慮しなければなりません。
充電スポットが少ない
電気自動車のバッテリーを充電できるスポットは、ガソリンスタンドと比べるとまだ少ないのが現状です。特に地方では充電スポットを見つけるのが難しく、長距離移動の際には燃料切れ(電欠)の不安があります。
電気自動車の普通充電には数時間かかることが一般的で、急速充電器を利用した場合でも約30分は必要です。そのため、事前に充電計画を立てておき、バッテリー残量に余裕を持って利用することが大切です。自宅マンションに充電設備が設けられている方も、他の居住者が利用していて「充電したいときにできない」ことがあり得るので、充電のタイミングには十分注意しましょう。
航続可能距離が短い
電気自動車は、エンジン車に比べて航続可能距離が短い傾向があります。フル充電した電気自動車の場合、一般的には100km~600km程度ですが、エンジン車は満タン時に500km~1,500kmの航続距離を確保できます。
そのため、長距離移動の際には、充電スポットの位置を事前に確認することが重要です。特に遠出をする場合には、途中で充電できる施設を探しながら走行する必要があり、エンジン車ほどの自由度は確保しづらいといえるでしょう。

電気自動車のデメリットを解消するには?
電気自動車を利用する際、上記に挙げたデメリットを解消するためには、以下の4つの方法が考えられます。
- 補助金を活用する
- 充電設備を整える
- 適切なシーンで利用する
- カーシェアリングサービスで電気自動車を利用する
それぞれ解説していきます。
補助金を活用する
電気自動車の車両価格は、エンジン車に比べて高い傾向があります。しかし、自治体の補助金や優遇税制を上手に活用すれば負担を軽減できます。補助金の内容は地域によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
充電設備を整える
充電スポットが少ないというデメリットを解消するには、自宅に電気自動車の充電器を設置するのも1つの選択肢です。充電器の価格や機能はさまざまで、設置にかかる費用も自治体の補助金を活用できる場合があります。また、計画的に充電を行うことで、航続可能距離の短さをさほど気にせず運用することも可能です。
適切なシーンで利用する
電気自動車は、旅行のような長距離・長時間の利用には不向きな場合があります。たとえば、渋滞時に電欠を起こす可能性があり、地域によっては充電スポットが見つからない、充電スポットが混雑していて完了まで時間がかかる、といったことがあるためです。
こうした状況では、航続可能距離が長く、給油がしやすいエンジン車やハイブリッド車が最適です。一方、電気自動車は日常生活での利用に適しており、近距離移動には特に便利でしょう。
カーシェアリングサービスで電気自動車を利用する
電気自動車は高額で充電設備も必要ですが、カーシェアリングサービスを利用すれば気軽に乗ることができます。特に都市部ではカーシェアで利用できる車種の選択肢が広がっており、電気自動車の普及にも貢献しています。たとえば、三井のカーシェアーズでは、「ニッサン リーフ」や「トヨタ bZ4X」などの電気自動車が利用可能です。

三井のカーシェアーズでメリットの多い電気自動車を気軽に利用しよう!
電気自動車は、環境負荷が低くメンテナンスもしやすいなど、多くのメリットがあります。しかし、初期費用が高く、充電スポットも限られているため、購入に踏み切れない方もいるのではないでしょうか。そのような場合には、カーシェアリングサービスを活用して電気自動車を利用する選択肢もあります。カーシェアリングサービスなら、高額な初期費用が必要なく、充電設備はステーションに設置されています。
特に都市部での日常使いに電気自動車を利用するなら、三井のカーシェアーズがおすすめです。三井のカーシェアーズでは、環境にやさしい電気自動車を手軽に利用できます。代表車種の「ニッサン リーフ」は満充電で約320kmの走行が可能で、走行中のCO2排出がゼロのため、環境負荷を抑えた移動が実現します。予約はスマートフォンから行えるので、利用開始から終了までの手続きもスムーズです。
利用中のトラブルにも24時間対応のサポート体制が整っており、充実した保険・補償制度も用意しているため、初めての電気自動車でも安心してドライブを楽しめます。環境に配慮した次世代の移動手段を、気軽に体験できるサービスとしてぜひご検討ください。

監修者:山城 利公(やましろ としまさ)
さまざまなカテゴリーのクルマを独自のスタンスで試乗評価。交通インフラ、物流業界の構造、安全運転教育など社会課題にも精通、モビリティ社会の未来に貢献している。物流のプロとして200万km(地球50周以上)無事故走行の実績を持つ。 AJAJ(日本自動車ジャーナリスト協会)会員